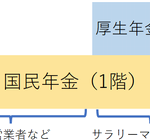公的な医療保険制度には主にサラリーマンやその家族などを対象とする健康保険(被用者保険・職域保険などとも言います)と、自営業者・年金受給者及びその家族などを対象とする国民健康保険(地域保健などともいいます)とがあります(そのほか75歳以上を対象とする後期高齢者医療保険制度などもあります)。
ここではサラリーマンやその家族などを対象とする健康保険(被用者保険)について、その特徴を簡単にご説明していきます。
健康保険(被用者保険)の基礎用語
健康保険は健康保険の適用事業所で働く従業員(公務員含む)やその家族の業務外のけがや病気にかかる医療費について給付を行う公的医療保険制度を言います。
健康保険の制度を理解するためには「保険者」「被保険者」「被扶養者」の三者を理解する必要があります。これらの用語ならびに健康保険に関する基本的な制度の概要はいかのようになります(日本健康保険協会HP「https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/」ほか参照)。
| 保険者 | 健康保険事業の運営主体のことを保険者といいます。一般企業の従業員の加入する健康保険の保険者には、おもに以下の2つがあります(このほか公務員を対象とした国家公務員共済組合・地方公務員共済組合などの共済組合も保険者となります)。
1.全国健康保険協会:会社や同業者などで独自の健康保険組合を保有しない企業(主に中小企業)の従業員やその被扶養者を対象とする健康保険の運営主体をいいます。会社などで独自の健康保険組合などを保有しない場合は必然的にこちらに加入することになります(特に協会管掌健康保険といいます)。 2.健康保険組合:会社や同業者などで独自の健康保険組合を保有する企業(主に大企業)の従業員やその被扶養者を対象とする健康保険の運営主体をいいます。 |
| 保険料 | 保険料は事業主と被保険者が折半で負担します(被保険者負担分や給与・賃金からの天引き)。保険料の納付は事業者が被保険者の負担分と合わせて翌月の末日までに納付します。
保険料の額は、被保険者の標準報酬月額(給与などに基づいて算定)に保険料率(都道府県ごとに異なる)を乗じて算定します。 |
| 医療費の支払い | 健康保険の被保険者や被扶養者が業務外の事由により病気やケガをしたときの医療費の支払いに対して給付を行います(業務上や通勤災害などによるものは原則として労災が適用されます)。
医療費の負担は原則として、自己負担3割(保険者負担7割)となります。また医療費の支払いが高額となるときは、自己負担分として支払った金額の一部が払い戻される高額療養費と呼ばれる制度もあります。 |
| 適用事業所 | 健康保険の適用は事業所単位に行われますが、すべての事業所が健康保険の適用を受けるわけではありません。 また法律上適用が強制される強制適用事業所(従業員を乗じ使用する法人や国・地方公共団体の事業所ほか、常時5人以上の従業員を使用する事業所など)と適用が任意となる任意適用事業所(強制適用事業所以外で健康保険・厚生年金保険の適用をうけることにつき許可を受けた事業所)とがあります。 |
| 被保険者と被扶養者 | 保険対象となるのは被保険者ならびに被扶養者の業務外の事由により病気やケガをした時の医療費の支払いです。 ここでいう被保険者は事業者(健康保険の適用事業所)に雇用されている社員や従業員で労働時間などで一定の要件をみたすものなどをいい、また被扶養者とは被保険者の配偶者(夫もしくは妻)や両親・子などの親族を言いますが、同居要件の有無により以下の通り分けられます。 同居要件なし:直系尊属(親や祖父母)、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されているもの。 |